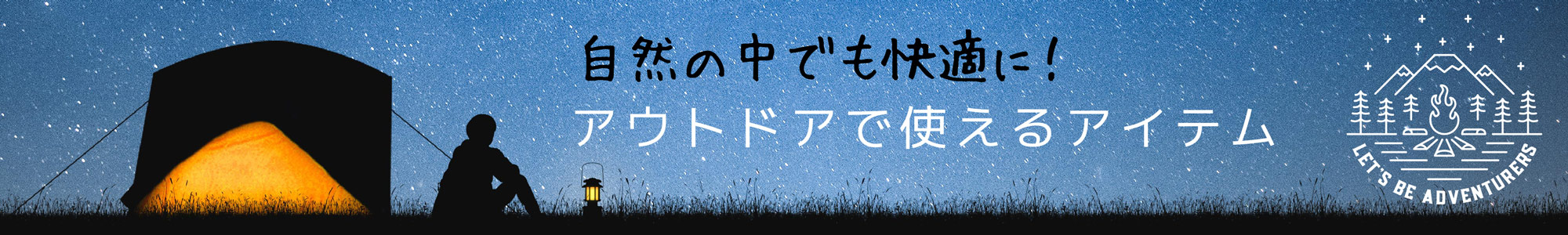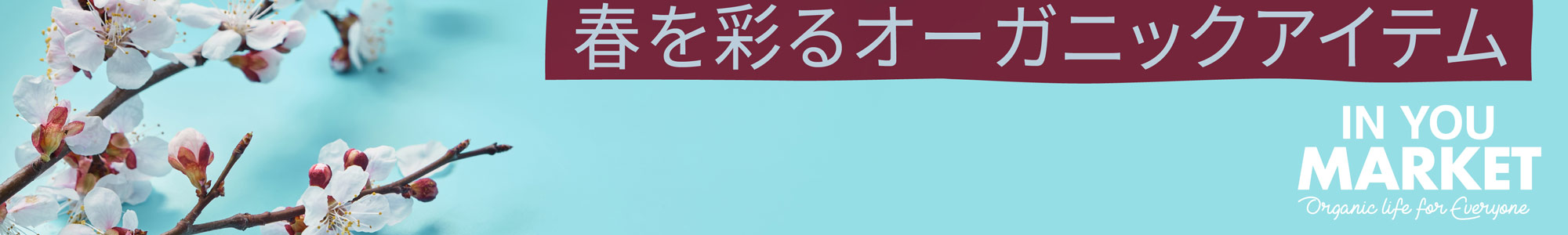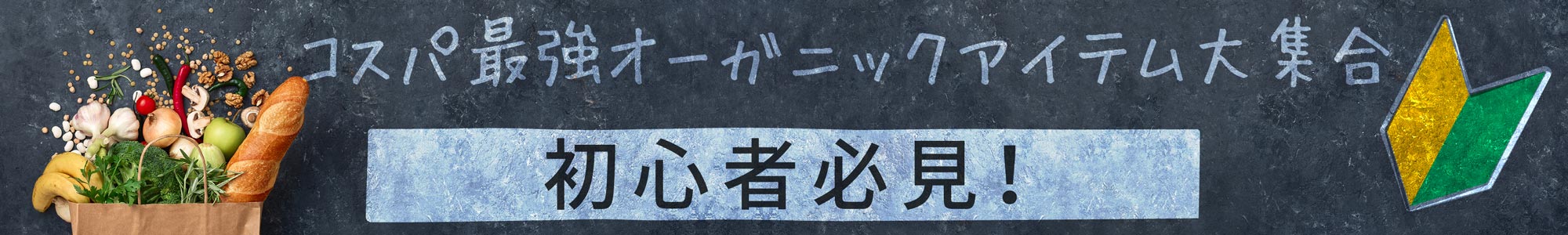- おすすめ
- 探す
- カテゴリから探す Search by category
- お悩みから探す Search by issue
- こだわりから探す Search by feature
- シーンから探す Search by pourpose
- ランキングから探す Search by ranking
- ヘルプ
- カスタマーサポート Customer support
- よくある質問 Q&A
- 初めての方へ
-
IN YOU Market について
![]()
- ニュースレター
- メールマガジンの登録
- オーガニックニュースなど
- インユージャーナルへ To IN YOU Journal
-
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
セール中の商品を見る








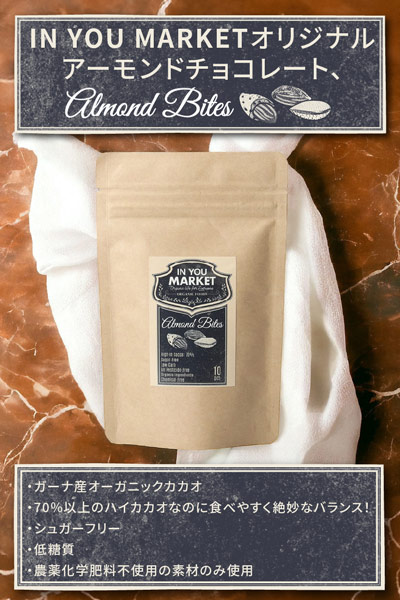






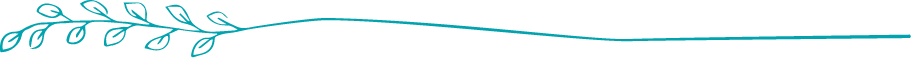
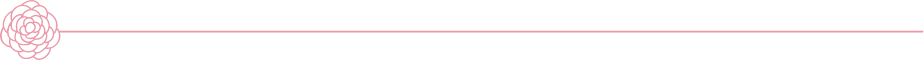









20210927_inyu_0381-m.jpg)