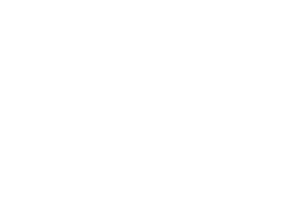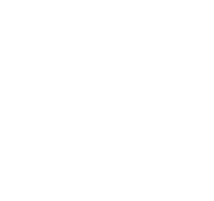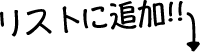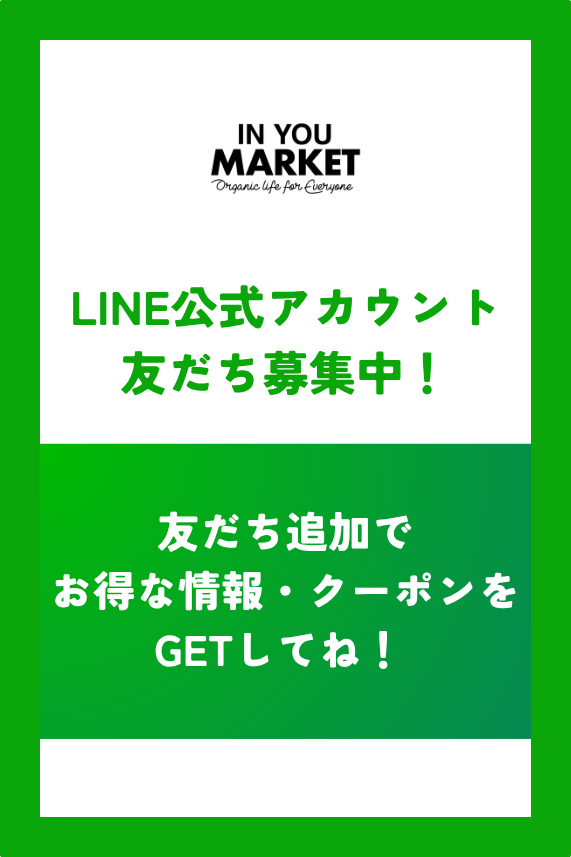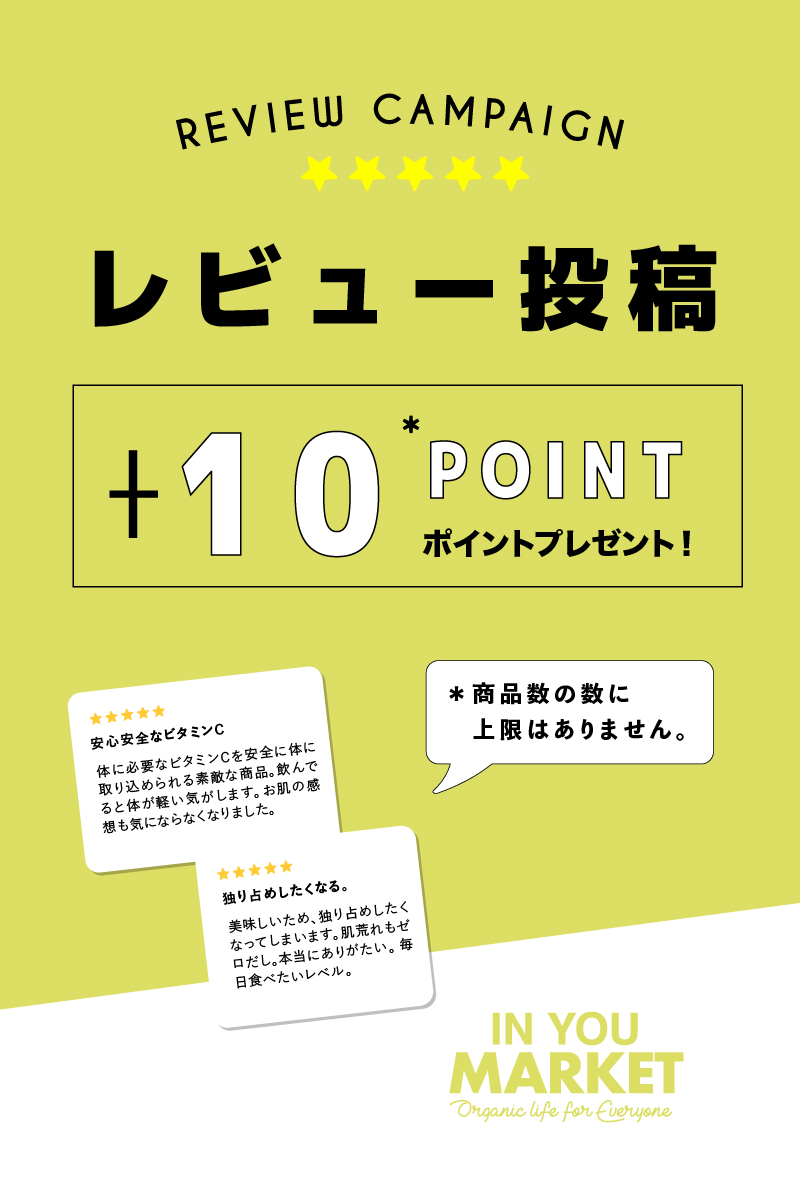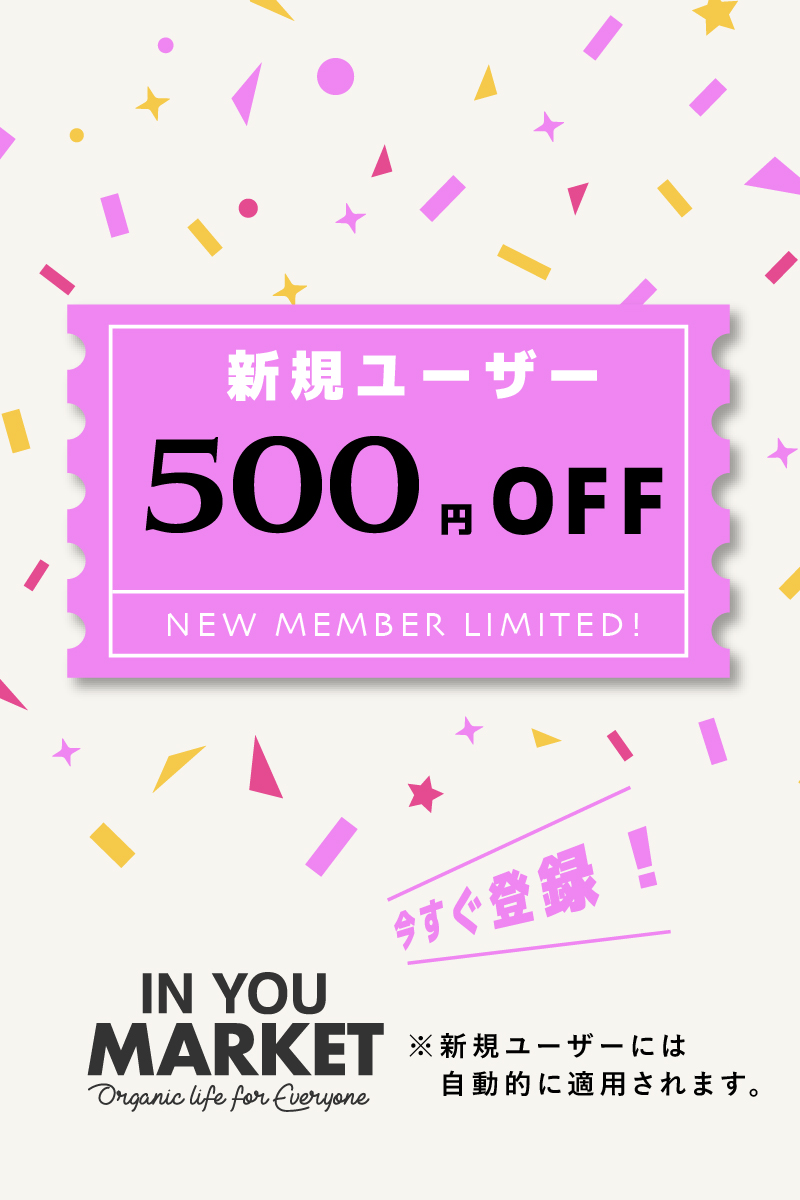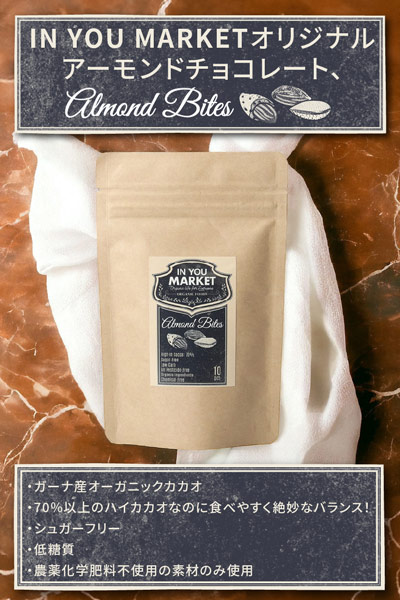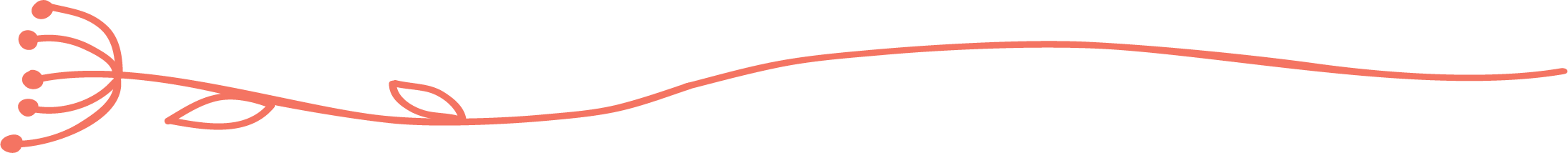天然木のスプーン(オリーブ材)小ぶりで口当たりやさしい、手仕事で仕上げた丁寧な逸品。スープや、デザート、離乳食におすすめのおしゃれカトラリー
天然木のスプーン(オリーブ材)小ぶりで口当たりやさしい、手仕事で仕上げた丁寧な逸品。スープや、デザート、離乳食におすすめのおしゃれカトラリー
通常配送料に550円(税込)が加算されます。
長さ:15cm
中東・ヨルダン産 オリーブの木
静かな朝、台所で手に取るのは、金属ではなく、オリーブの木目が走る、一本のスプーンだったとしたらどう思いますか?
熱を伝えにくく、器と触れても音を立てない。
口に含んだ瞬間、料理の香りだけが立ち上ります。このスプーンは、中東ヨルダンのオリーブの木から生まれ、難民の人たちの確かな手仕事で形になりました。
あえて、大ぶりではなく、日本の食卓になじむ小さめサイズ。
あなたの料理はまだ「金属の味」をまとっている?素材が味覚を左右し、音も熱もストレスも減らす木のスプーンが台所の常識を塗り替える
「台所の心地よさ」は、素材選びの一つで意外と大きく変わります。
例えば、よく見る金属のスプーンは一般的に入手しやすく、安価なものも多いですよね。
丈夫で便利ですが、熱をすばやく伝え、器に触れるたびに小さな音を生み、口当たりに金属感を残すことがあります。
忙しい朝なら、微細なストレスに気づきませんが、食べる体験は五感の積み重ね。いっぽう木のスプーン、とくに今回ご紹介する、緻密な木目をもつオリーブは、熱をゆっくり伝え、器との当たりがやさしく、口当たりがまろやかになる特徴があります。
しかも日本の食卓に合わせた小ぶりさなら、デザート、スープ、ヨーグルト、離乳食まで万能に、使いまわせます。
燃やされていた資源が仕事と道具になった日。ヨルダンのオリーブから、日本の食卓へ届くまでに起きたサステナブルな逆転
ヨルダンではオリーブが国の果樹の主役。
統計では、果樹面積の約72%をオリーブが占め、約1,100万本が育つと報じられています。
日本では比較的高級品扱いをされる、豊富なオリーブ材は、現地で剪定や伐採の後に薪として燃やされてしまうことも多かったのだそう。
このスプーンは、見過ごされてきた木に工芸としての命を吹き込む試みから生まれました。
オイルの国の資源を、日本の食卓が日常的に使う道具に。
長く使える一品は、買い替え頻度を下げる=環境負荷の逓減にもつながる利点があります。
言葉より手元で通じた日。アラビア語の工房で、シリアの職人が教えてくれた「削りの基準」。一本のスプーンが完成するまで
最初は機械が思うように動かず、厚みのムラが出ました。スプーンは口に入れる道具なので、1ミリの段差が違和感になってしまいます。
特に日本人は外国人と比較しても、シビアな方が多いので、丁寧さが求められる。
そこで、運よく、シリア出身の高い技術を持つ職人さんと出会い、工程づくりを一緒にお願いしました。そして、「どこまで薄くするか」「どの面を残すか」まで、細かく決めていきました。
彼はやがてイタリアへ。
でも残してくれた基準と手順は工房に残りました。
乾燥は自作の乾燥庫で最長2週間程度。
割れを避けながら水分を抜き、3人で分業して1日で仕上げまで運びます。アラビア語が飛び交う現場で、元々慣れない作業だったけれど、今では、日本人の基準に合わせて、本当に細部にこだわってくれる。
日本のユーザーに渡すと伝えると、「じゃあ、もっと丁寧に」と研磨の手が静かに速くなるんです。その姿を見てこの事業への確信が持てました。
そう語るのは木材を使った商品を作る工房を立ち上げた日本人オーナーの大橋さんです。
食べる道具を替えた瞬間から体験が変わる「感覚設計」という発想
研究では、カトラリーの素材が味の感じ方に影響することが報告されています。
金属の種類や素材で、甘味・塩味・金属っぽさの知覚が変わるという知見です。
木のスプーンは金属的なオフフレーバーを抑えられるため、料理の香味をそのまま受け止めやすい、そう考えると腑に落ちます。
さらに、木は金属より熱を伝えにくいので、口元が熱くなりにくく、器と触れても音が響きにくいわけです。
木の温もりを用いたストレスのない、やさしい食事は、忙しい日々のコンディションを整えてくれるはずです。
オリーブスプーンで叶える“静かなごちそう時間”の作り方
具体的な使い方(行動提案・少数の箇条書き)
スープ&ポタージュ...熱が伝わりにくいのでゆっくり味わえます。
デザート...プリン・ヨーグルト・グラノーラなど、器との衝突音を軽減してくれます。
離乳食・介護食...口当たりがやわらかく、小ぶりで量の調整がしやすいです。
小皿に盛り付けられるサイズのおかずの取り分け...金属音を立てず、器を傷つけにくい傾向があります。
木の道具との付き合い方「道具は買うより育てる時代へ」―オイルケアで艶が戻る、続く美しさの手引き
お手入れ
洗い方は、オーガニックや無添加の中性洗剤がおすすめ。ぬるま湯でやさしく。浸け置き・食洗機・乾燥機は不可です。
布で拭いてから自然乾燥し、直射日光は避けてください。
乾燥が気になったら、食品に使えるココナッツオイル、オリーブオイルなどを薄く伸ばして拭き取ります。
避けたいこと:長時間の煮沸、直火、電子レンジは避けてください。
思ったより安全で、思ったより都会。
「行ってみた家族が驚いた」意外とオープンな雰囲気のヨルダンの日常
製品の発案者であり、現地で工房を立ち上げた大橋さんによると、ヨルダンは地域の中でも落ち着いた国情であり、生活インフラが整っているといいます。
電気や水に困ることはほとんどなく、首都ではスーパーやカフェ、レストランの選択肢も十分。
様々な外国人が多く暮らしているため、英語対応の店も多く、日常の買い物や外食に不便を感じにくいのだそう。
実際日本から彼女の家族や友人が訪れたとき、彼らが口をそろえて驚いたのは「治安の良さ」と「想像以上の都会っぽさ」だったそう。
世界遺産ペトラを見て感嘆し、帰るころには「思っていた中東のイメージと違った!」と笑っていたといいます。
遠いニュースで知った国が、思っていたよりも人の営みがきちんと続く日常、そんなギャップは、心をやわらげてくれます。
著者の私もヨルダンに対してはこのお話を聞くまでは、無知だったが故に、もっと治安が悪かったり、不便さがあるものなんじゃないかと、なんとなく内心イメージしてしまっていました。
けれど話を聞いて、日本人にとっても暮らしやすい実態は意外に感じました。
また彼女は、ヨルダンが国際機関やNGOの拠点として人が集まりやすい場所だと話します。
近隣国の情勢が揺らぐと、ヨルダンに拠点を置き直すケースもあるため、多国籍の人びとが行き交う空気が日常にあり、日本人が道を歩いても珍しがられることは少なく「誰がいてもおかしくない」オープンな感じのムードがあるのだそう。
こんな当たり前に多様性のある空気は、オリーブの手仕事にも穏やかに影響しているのではないかと思います。
違う文化的背景をもつ人同士でも、同じ作業台を囲んで同じ商品作りを行い、同じ基準を共有できる。
そんな前提があるからこそ、一本のスプーンに国境を越えるやさしさが宿っていくのかもしれません。
「買う=彼らの支援に加わる」という選択
遠いニュースだった難民の現実が、毎日の食卓で手触りになる瞬間
このスプーンは、オーガニックな暮らしを広げるというIN YOU MARKETの私たちの理念に沿って、高い透明性(素材=ヨルダンのオリーブ/製造=現地工房の手仕事)、持続可能性と就労の循環(難民の人たちの“仕事”を生む工程設計)を土台に生まれました。
「静かな一匙」が、あなたの食卓の体験と、遠くの誰かの今日の仕事を同時に支えます。道具を選ぶことは、生き方を選ぶことです。
ぜひ一本、大切な人や、自分への贈り物を、迎えてください。
最初のレビューを書いてみませんか?