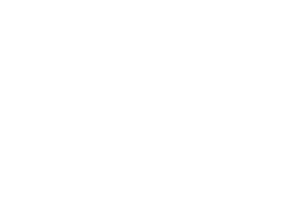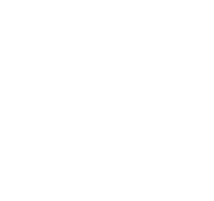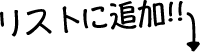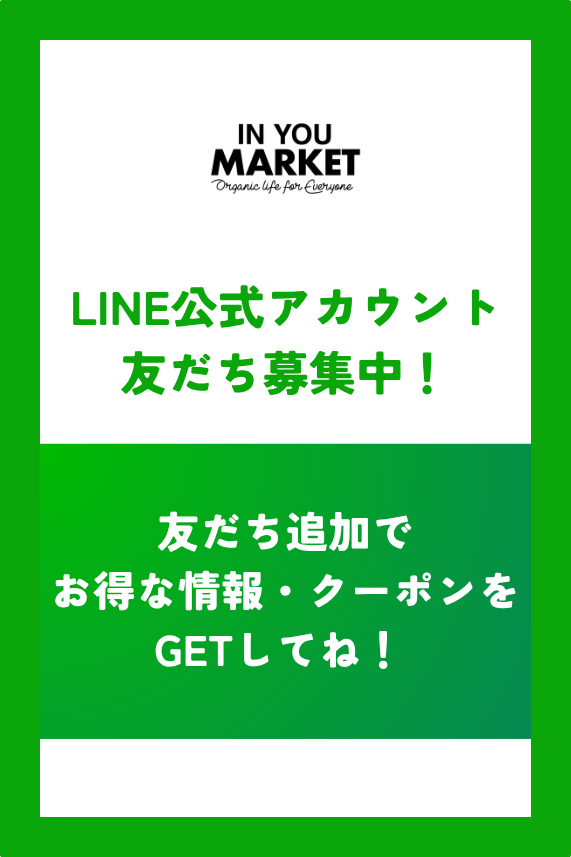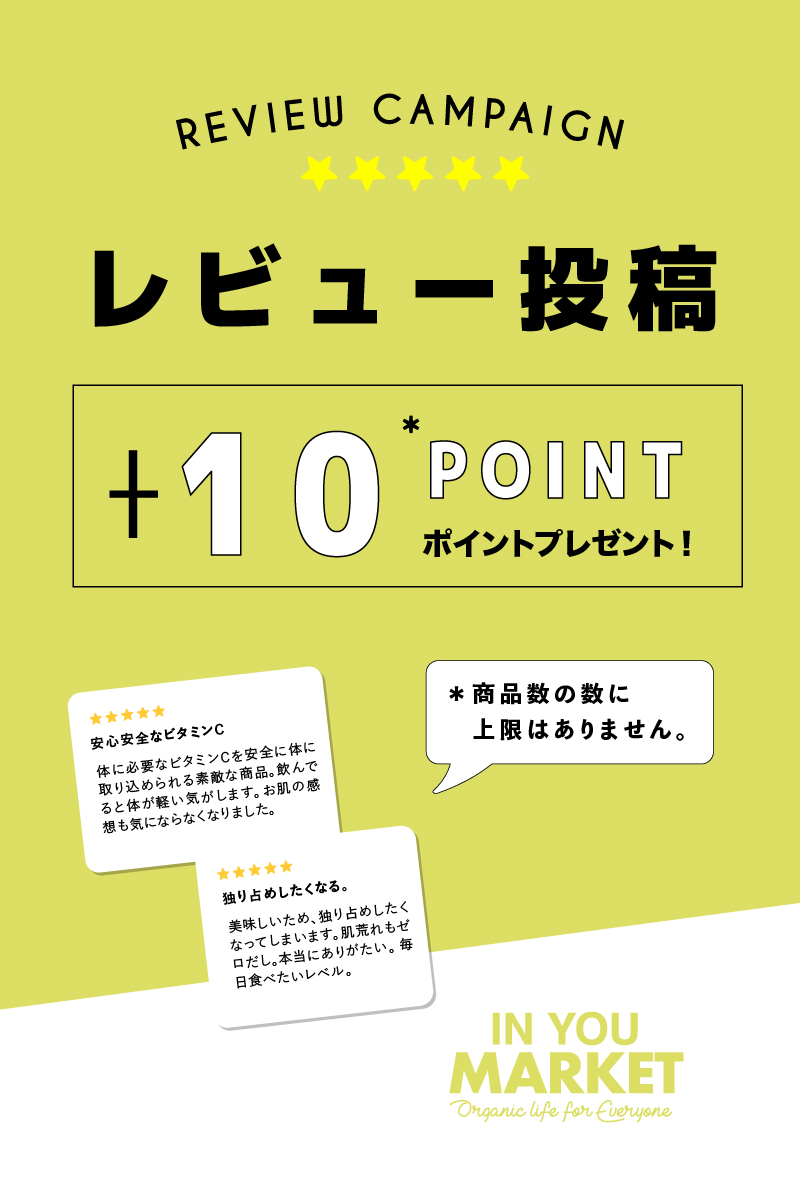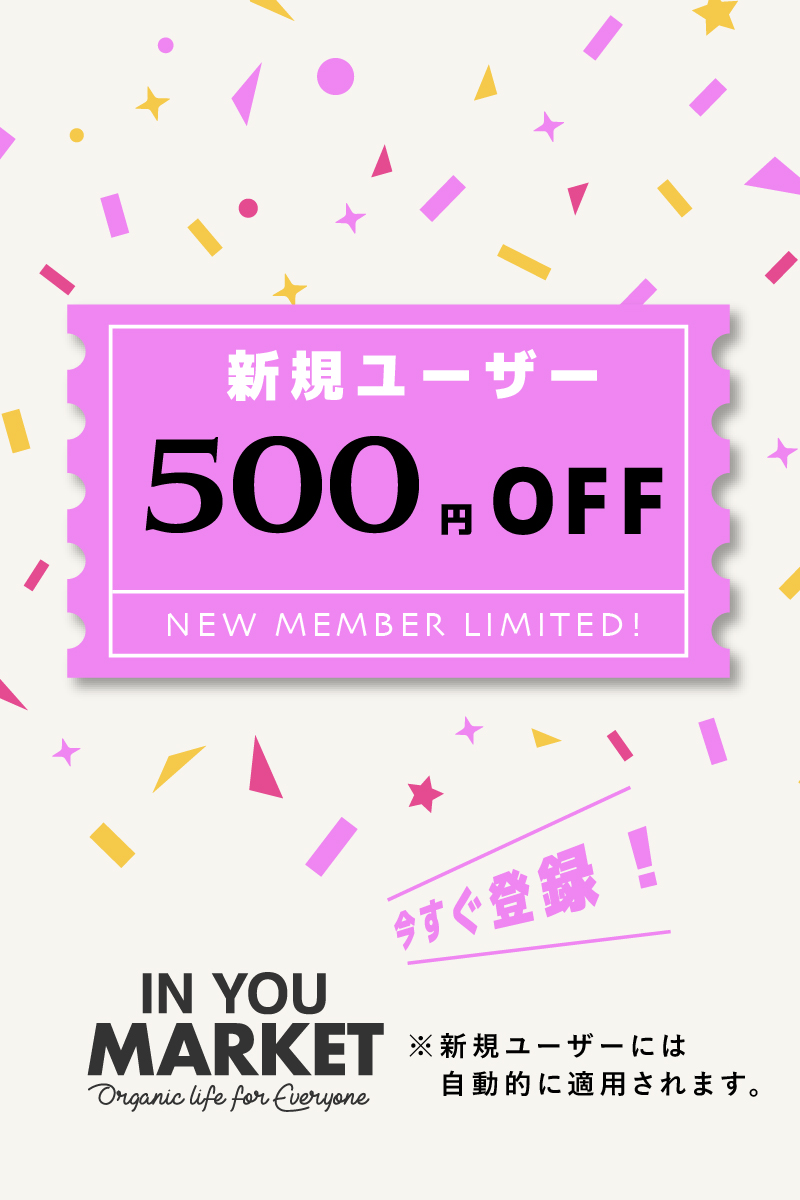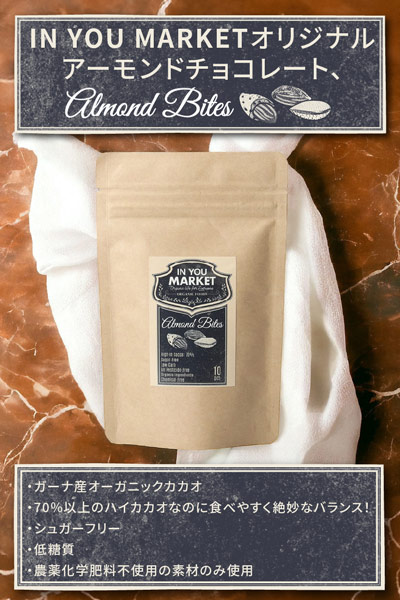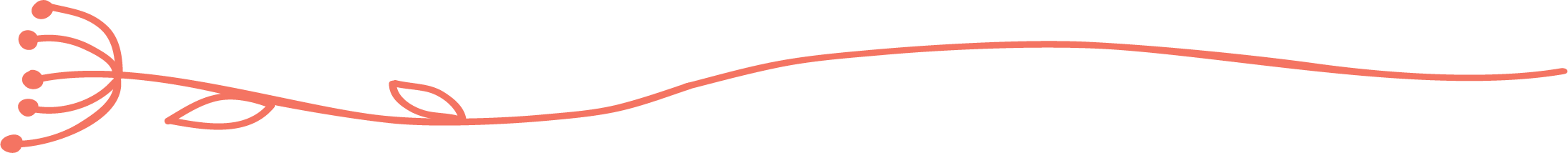日本一の玉ねぎ産地「淡路島産」有機玉ねぎ5kg|全国の料理人が認めるブランド「自然をまるごと生かしたい」オーガニック農家が30年以上続けて農薬に頼らず守り抜いた誇り。
通常配送料に550円(税込)が加算されます。
淡路島産有機玉ねぎ5kg
今や”全国ブランド”とも言われるほどの名高い淡路島の玉ねぎ。その裏でほんのわずかしか出回らない「有機栽培」の現実とは
淡路島産の玉ねぎといえば、今や有名シェフやグルメな人たちがこぞって取り寄せるほどのブランド野菜として頻繁に耳にするかもしれません。
私たちが普段から手に取る機会の多い“玉ねぎ”という素材を、淡路島の風土はしっかりと育て上げてきました。
ただ、そんな有名ブランドの大多数は実際、効率や収量を重視しながらも、昔よりは減ったとはいえ化学肥料や農薬に頼る栽培方法がメインでした。
薬に頼るだけじゃ、これからの日本農業は立ち行かない。山の中で有機JASをひたむきに守り抜く淡路島の玉ねぎが伝えたい希望。
一方で、淡路島の中でも限りなく自然に近いかたちの農法、いわゆる「有機JAS認定」を得ている玉ねぎは、実はあるごくごく非常に希少な作り手の努力によって支えられてきたという現状があります。
長年、農業者向けの指導には農協が関わってきたこともあり、生産量を安定させるための化学肥料や薬は、大なり小なり使用してきた歴史がありました。
そうした背景のもと、30年以上も前から“土を守りたい”という志だけでオーガニック栽培に切り替えた人は、出品者の方の周囲にも、ほとんどいませんでした。
「え、料理の定番、玉ねぎでさえ、オーガニック栽培は難しいんだ..。」と、おそらく、多くの人にとっては驚く話かもしれません。
でも、実は、全国で見ても生産者の高齢化や人手不足が加速し、化学肥料を使えば管理がラクで収量も安定しやすいことから、その大量生産の方向に頼る方が圧倒的に楽なのです。
最近では、農地を諦めて宅地や商業地に転用する動きも増えているため、本当のオーガニック栽培へ舵を切るには、まるで孤軍奮闘のような心境にならざるを得ないといいます。
しかし、そんな中であえて農薬を最小限に抑え、自然に負担をかけない方法を突き詰め続ける農家が淡路島にほぼ、唯一、存在します。
私はこのお話を聞くうちに、「オーガニックや淡路島自体がブランド化されてきたから売りたい」などという単純な商業的理由などではなく、「未来の地球を守りたいからこそ、薬に頼らない栽培を貫きたいんだな・・」という熱意を感じずにはいられなくなりました。
30年以上前から、薬まみれの畑を疑問視してきた農家の挑戦「これじゃ土が死んでしまう」という直感を捨てられなかった農家があえて孤独に負けず、闘い続けた
作り手および出品者がオーガニックに目覚めたのは、まだ日本国内で有機JASなど意識されていない時代でした。
農協の指導では、農薬や化学肥料を上手に使うことで玉ねぎを効率的に育てるのが当たり前とされていた時代です。
「このまま土をいじめ続けたら、いつか限界が来るのではないか...」という疑問が当時から消えなかったそうです。
やがて自身で土を観察し始めるうちに、少しずつ化学肥料を減らし、有機質肥料を使って微生物の力を生かす栽培へ切り替えようと決意を固めていきました。
もちろん、現場は一筋縄にはいきません。
化学肥料を断ち、農薬も使わないかわりに雑草が生えまくり、病気や害虫の脅威にさらされ、人手や時間を大量に投じなければならなくなるからです。ましてや周囲の畑が従来型の栽培を続けていれば、風や水路を通じて薬剤が流れ込むリスクもあり、想像以上に正真正銘のオーガニック栽培を維持するのは険しい道のりで、厳しい現実が立ちはだかりました。
それでも「土が死に自然環境がおかしくなるのを、放っておけない」と粘り強く挑んだ末、長年かけて有機JAS認定を取得できるほどの畑をつくり上げました。
しかも、その畑は淡路島各地に点在する山間部など、周囲に他の農家がいないような場所を厳選し、水の管理も一から見直して守られています。
ほんの少しの手違いや、周囲の環境のわずかな変化が認証剥奪につながるリスクを抱えながら、「ひとりでもこの道を貫こう」という覚悟が今も続いているのです。
幻の有機玉ねぎがなぜ表に出なかったのか?手間とコストに見合わないとされ、隠れた存在だったオーガニック玉ねぎ。加工用に回されていた幻がやっと個人宅へ届けられる時が来た!
実は、この農家が育てた有機玉ねぎは、元々は全国の加工工場などにのみ出荷されていました。
大量生産をしないぶん、安定して出荷量を増やすのは難しく、一般家庭に流通させるだけの余力がなかったのです。
農業の現場では収穫後の保管や選別、出荷のための梱包など、すべてに手間がかかるため、小規模生産だと個人向けに対応するのはほぼ不可能と言われてきました。
その間、流通の面でサポートをしてきた方が、「このまま加工用だけではもったいない。消費者に直接届ければこそ、オーガニックの価値や作り手の思いが伝わるのではないか...」と提案を始めたのがちょうど、10年ほど前のことです。
もちろん、最初は設備も資金も人手も足りませんでしたが、少しずつ畑を増やし、厳選された山間部での栽培面積を拡大しながら、ようやく個人が通販で手に取れるほどの出荷量が整ってきたのです。
これにより、観光で淡路島に訪れなくても「有機JASの淡路島玉ねぎ」を自宅まで取り寄せられるようになりました。
そんな一歩を踏み出せたのは、生産者と流通担当者双方が「有機栽培に価値があると共感してくれる消費者にこそ、本当の意味で食材の力をお届けしたい」という思いを共有しているからに他なりません。
化学肥料で肥大化を急ぐより、土と微生物に任せた方が深い旨みが育つ。わざとらしく作られた旨み至上主義じゃないからこそ、じわっと染み込む味が生まれる。有機栽培がくれる本物の風味。
多くの方が気にする「オーガニックっておいしいの?」という質問については、もちろん個人的には、独特の味の濃さや苦味が少ないケースも多く、野菜本来の野生的な味や力強さが引き出されていて、美味しいと思っています。
とはいえ、出品者自身としては、「実は、そこだけが目的じゃないんです。」と強調します。
というのも、農薬を使わないから美味しくなる、化学肥料を減らしたから甘くなる、といった単純な話ではなく、「土と自然への負荷を極力抑えた結果としてできあがるのが有機野菜である」という考え方が先だからです。
また、物理的には、過度に急激な肥大化をさせないことで、玉ねぎ本来の風味が詰まった状態に仕上がる傾向があるようです。
水分量が多く、生でスライスしても辛味は比較的マイルドで、炒めると甘みがぐっと出やすいと感じる方が多いとのこと。
便利さや見た目のきれいさだけを追求しない自然が織りなす本当のおいしさというのは、日常の食卓にちょっとした感動をもたらしてくれるものです。
皮をむくと現れる玉ねぎの透明感、切ったときに涙が出るのは玉ねぎの宿命ではありますが、その後口に入れた時の自然な甘さや、じわっと出る水分の量に「これが“薬を使わない土”で育った証なのかもしれない」と思わず納得してしまいます。
高齢化と人手不足などの日本農業の深刻な壁。誰もがもう農業は儲からないと諦めかける時代に、あえて、薬に頼らず挑み続ける。
次世代の食卓を変えるのは”あなたのお買い物
実は、この農家が育てた有機玉ねぎは、元々は全国の加工工場などにのみ出荷されていました。
最初のレビューを書いてみませんか?
淡路島産有機玉ねぎ5kg

今や”全国ブランド”とも言われるほどの名高い淡路島の玉ねぎ。その裏でほんのわずかしか出回らない「有機栽培」の現実とは
淡路島産の玉ねぎといえば、今や有名シェフやグルメな人たちがこぞって取り寄せるほどのブランド野菜として頻繁に耳にするかもしれません。
私たちが普段から手に取る機会の多い“玉ねぎ”という素材を、淡路島の風土はしっかりと育て上げてきました。
ただ、そんな有名ブランドの大多数は実際、効率や収量を重視しながらも、昔よりは減ったとはいえ化学肥料や農薬に頼る栽培方法がメインでした。
薬に頼るだけじゃ、これからの日本農業は立ち行かない。山の中で有機JASをひたむきに守り抜く淡路島の玉ねぎが伝えたい希望。
一方で、淡路島の中でも限りなく自然に近いかたちの農法、いわゆる「有機JAS認定」を得ている玉ねぎは、実はあるごくごく非常に希少な作り手の努力によって支えられてきたという現状があります。
長年、農業者向けの指導には農協が関わってきたこともあり、生産量を安定させるための化学肥料や薬は、大なり小なり使用してきた歴史がありました。
そうした背景のもと、30年以上も前から“土を守りたい”という志だけでオーガニック栽培に切り替えた人は、出品者の方の周囲にも、ほとんどいませんでした。
「え、料理の定番、玉ねぎでさえ、オーガニック栽培は難しいんだ..。」と、おそらく、多くの人にとっては驚く話かもしれません。
でも、実は、全国で見ても生産者の高齢化や人手不足が加速し、化学肥料を使えば管理がラクで収量も安定しやすいことから、その大量生産の方向に頼る方が圧倒的に楽なのです。
最近では、農地を諦めて宅地や商業地に転用する動きも増えているため、本当のオーガニック栽培へ舵を切るには、まるで孤軍奮闘のような心境にならざるを得ないといいます。
しかし、そんな中であえて農薬を最小限に抑え、自然に負担をかけない方法を突き詰め続ける農家が淡路島にほぼ、唯一、存在します。
私はこのお話を聞くうちに、「オーガニックや淡路島自体がブランド化されてきたから売りたい」などという単純な商業的理由などではなく、「未来の地球を守りたいからこそ、薬に頼らない栽培を貫きたいんだな・・」という熱意を感じずにはいられなくなりました。
30年以上前から、薬まみれの畑を疑問視してきた農家の挑戦「これじゃ土が死んでしまう」という直感を捨てられなかった農家があえて孤独に負けず、闘い続けた
作り手および出品者がオーガニックに目覚めたのは、まだ日本国内で有機JASなど意識されていない時代でした。
農協の指導では、農薬や化学肥料を上手に使うことで玉ねぎを効率的に育てるのが当たり前とされていた時代です。
「このまま土をいじめ続けたら、いつか限界が来るのではないか...」という疑問が当時から消えなかったそうです。
やがて自身で土を観察し始めるうちに、少しずつ化学肥料を減らし、有機質肥料を使って微生物の力を生かす栽培へ切り替えようと決意を固めていきました。
もちろん、現場は一筋縄にはいきません。
化学肥料を断ち、農薬も使わないかわりに雑草が生えまくり、病気や害虫の脅威にさらされ、人手や時間を大量に投じなければならなくなるからです。ましてや周囲の畑が従来型の栽培を続けていれば、風や水路を通じて薬剤が流れ込むリスクもあり、想像以上に正真正銘のオーガニック栽培を維持するのは険しい道のりで、厳しい現実が立ちはだかりました。
それでも「土が死に自然環境がおかしくなるのを、放っておけない」と粘り強く挑んだ末、長年かけて有機JAS認定を取得できるほどの畑をつくり上げました。
しかも、その畑は淡路島各地に点在する山間部など、周囲に他の農家がいないような場所を厳選し、水の管理も一から見直して守られています。
ほんの少しの手違いや、周囲の環境のわずかな変化が認証剥奪につながるリスクを抱えながら、「ひとりでもこの道を貫こう」という覚悟が今も続いているのです。
幻の有機玉ねぎがなぜ表に出なかったのか?手間とコストに見合わないとされ、隠れた存在だったオーガニック玉ねぎ。加工用に回されていた幻がやっと個人宅へ届けられる時が来た!
実は、この農家が育てた有機玉ねぎは、元々は全国の加工工場などにのみ出荷されていました。
大量生産をしないぶん、安定して出荷量を増やすのは難しく、一般家庭に流通させるだけの余力がなかったのです。
農業の現場では収穫後の保管や選別、出荷のための梱包など、すべてに手間がかかるため、小規模生産だと個人向けに対応するのはほぼ不可能と言われてきました。
その間、流通の面でサポートをしてきた方が、「このまま加工用だけではもったいない。消費者に直接届ければこそ、オーガニックの価値や作り手の思いが伝わるのではないか...」と提案を始めたのがちょうど、10年ほど前のことです。
もちろん、最初は設備も資金も人手も足りませんでしたが、少しずつ畑を増やし、厳選された山間部での栽培面積を拡大しながら、ようやく個人が通販で手に取れるほどの出荷量が整ってきたのです。
これにより、観光で淡路島に訪れなくても「有機JASの淡路島玉ねぎ」を自宅まで取り寄せられるようになりました。
そんな一歩を踏み出せたのは、生産者と流通担当者双方が「有機栽培に価値があると共感してくれる消費者にこそ、本当の意味で食材の力をお届けしたい」という思いを共有しているからに他なりません。
化学肥料で肥大化を急ぐより、土と微生物に任せた方が深い旨みが育つ。わざとらしく作られた旨み至上主義じゃないからこそ、じわっと染み込む味が生まれる。有機栽培がくれる本物の風味。
多くの方が気にする「オーガニックっておいしいの?」という質問については、もちろん個人的には、独特の味の濃さや苦味が少ないケースも多く、野菜本来の野生的な味や力強さが引き出されていて、美味しいと思っています。
とはいえ、出品者自身としては、「実は、そこだけが目的じゃないんです。」と強調します。
というのも、農薬を使わないから美味しくなる、化学肥料を減らしたから甘くなる、といった単純な話ではなく、「土と自然への負荷を極力抑えた結果としてできあがるのが有機野菜である」という考え方が先だからです。
また、物理的には、過度に急激な肥大化をさせないことで、玉ねぎ本来の風味が詰まった状態に仕上がる傾向があるようです。
水分量が多く、生でスライスしても辛味は比較的マイルドで、炒めると甘みがぐっと出やすいと感じる方が多いとのこと。
便利さや見た目のきれいさだけを追求しない自然が織りなす本当のおいしさというのは、日常の食卓にちょっとした感動をもたらしてくれるものです。
皮をむくと現れる玉ねぎの透明感、切ったときに涙が出るのは玉ねぎの宿命ではありますが、その後口に入れた時の自然な甘さや、じわっと出る水分の量に「これが“薬を使わない土”で育った証なのかもしれない」と思わず納得してしまいます。
高齢化と人手不足などの日本農業の深刻な壁。誰もがもう農業は儲からないと諦めかける時代に、あえて、薬に頼らず挑み続ける。
次世代の食卓を変えるのは”あなたのお買い物
実は、この農家が育てた有機玉ねぎは、元々は全国の加工工場などにのみ出荷されていました。
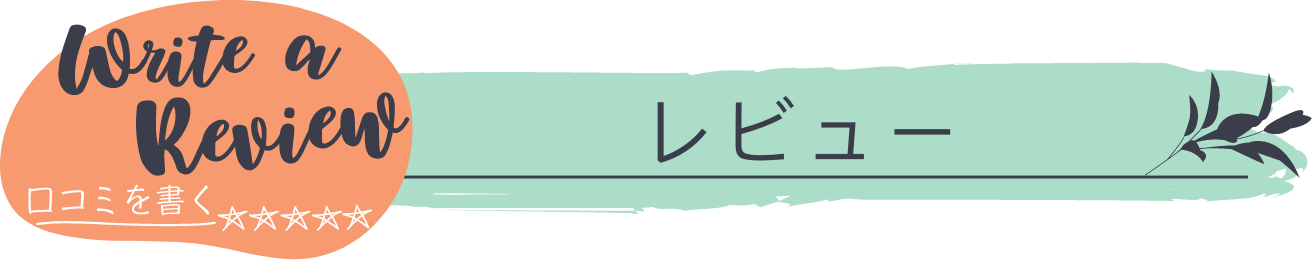
最初のレビューを書いてみませんか?