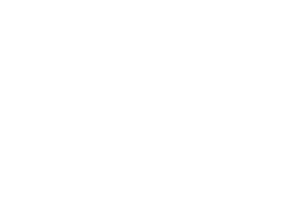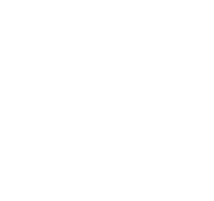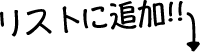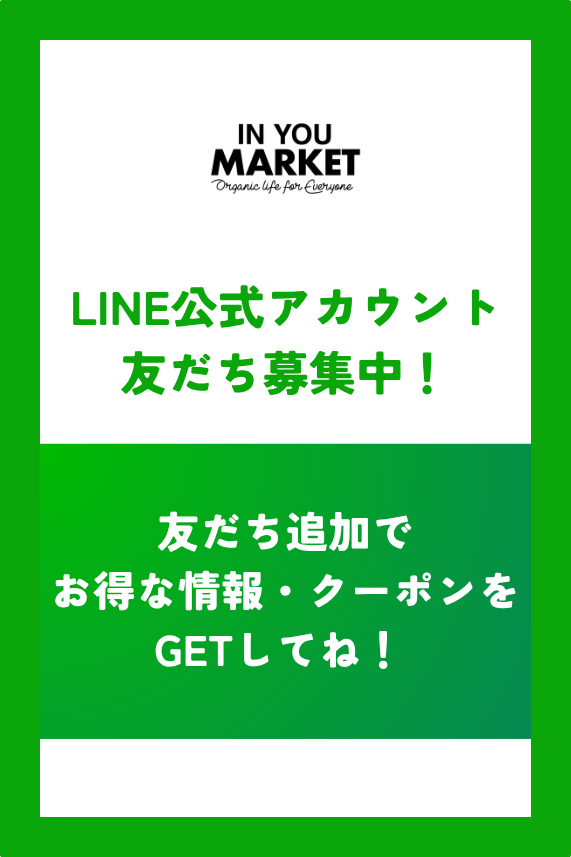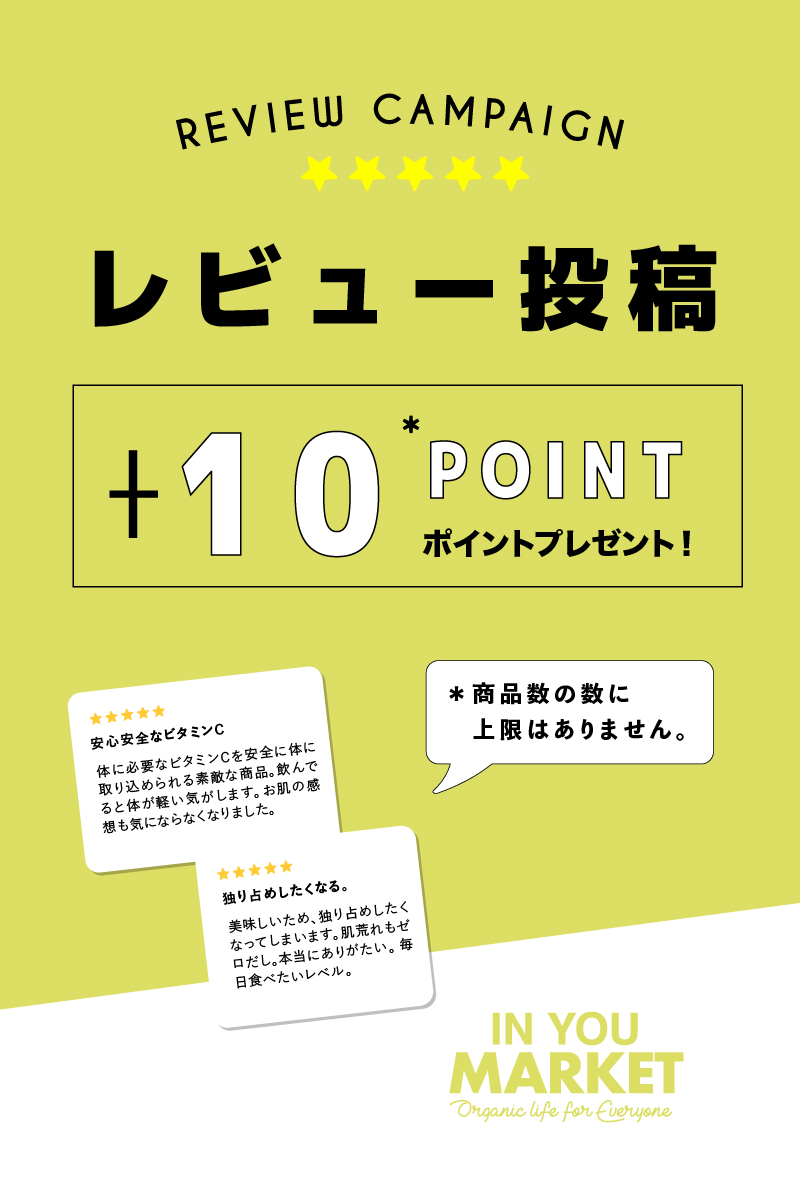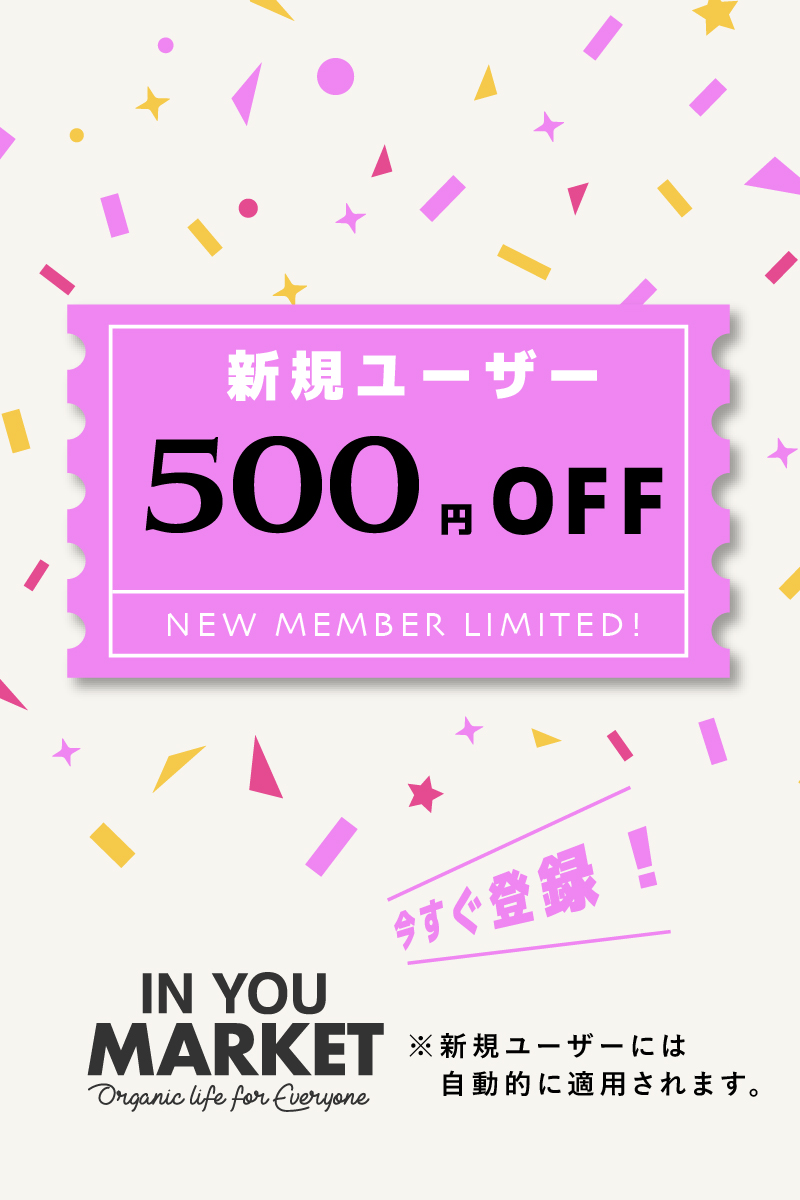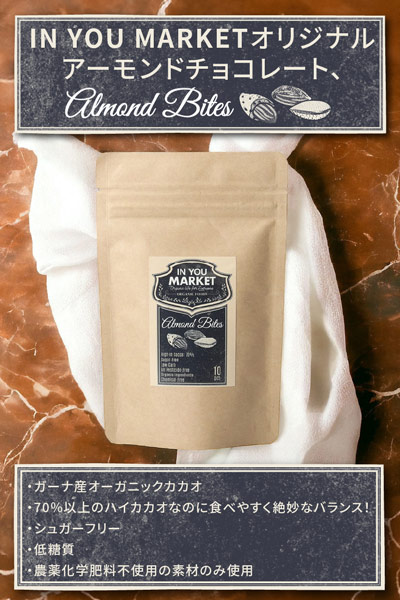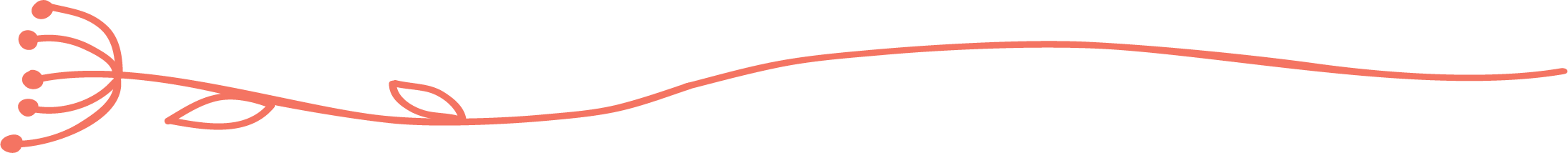木のしゃもじ|台所からはじまる連帯。ヨルダンのオリーブ材×手しごとで、ご飯が“ごちそう”に変わる
通常配送料に550円(税込)が加算されます。
長さ:30cm
中東・ヨルダン産 オリーブの木
プラスチックのしゃもじを手放した日から、毎日ご飯が特別になり、人と社会の距離まで縮まっていく木の一振りの話
健康やサステナブルに敏感なIN YOU MARKETユーザーの皆さまへ。
今日の主役は「オリーブ材のしゃもじ」。
毎日のご飯の満足度、そしてものづくりに関わる人たちへのリスペクトに、思いのほか大きく触れてくる道具です。
その当たり前は、本当に心地よいですか?
忙しい夜、よそい方で味が変わる?台所で見落としてきた最後の1%を取り戻す、小さな主役
多くの家庭で使われるのはご飯粒がくっつかない、洗いやすいことでトレンドのプラスチックのしゃもじです。
軽くて扱いやすい、洗いやすい、確かに現代の発明品は、便利です。
けれど、よそう所作の心地よさや鍋肌へのやさしさ、食卓に置かれたときの佇まいまで含めて考えると、「木製」という選択肢は私たちが思うよりも合理的。
中でもオリーブ材は緻密で摩耗に強く、日常の使い込みに耐える頼もしさがあります。
また、ノンスティック鍋や釜のコーティングは、細かな傷からも劣化してしまいます。
しゃもじが木製であることは、実は道具全体の寿命をのばす選択でもあるのです。
炊き上がりは完璧でも、最後のひと混ぜで差がつく。ご飯の粒立ちと艶を奪うのは、道具と所作のちょっとした摩擦
炊き上がった米の艶と香りは、よそう道具の材質と混ぜ方でも変わります。硬い樹脂で強く叩けば粒はつぶれやすく、鍋肌のコーティングも傷むリスクが上がります。
木のしゃもじは、面で受け止め、ほぐしたり、立たせる所作を自然に誘導し、湯気と香りの立ち上がりが穏やかに続き、食卓に運ぶまでのおいしい時間が伸びます。
さらに意外な視点を一つ。
食べる時に食材が美味しいかどうかだけでなくちょっとした、食の儀式性(Ritual)は「味の体験」を高めるという、行動科学の知見があります。
炊き上がりの釜にしゃもじを湿らせて呼吸を合わせてしゃっ、しゃっとほぐす。繰り返す所作が日々の晩御飯に、ごちそう感を立ち上げるのですね。
道具選びは気分だけじゃない。研究が示す木製表面のふるまいと、家庭の衛生管理のヒント
木とプラスチック、食材に触れる台所の表面でどちらが清潔か?
これは、長年議論されてきたことです。
代表的な研究では、木製表面は洗剤と温水での洗浄が有効であることが報告されています(まな板を対象とした研究)。もちろん、すぐ洗ってしっかり乾かすという基本がいちばん効きます。一方、ノンスティック調理器具の推奨道具として、メーカーは木製を挙げます。耐久性とコーティング保護の観点から、しゃもじも木に軍配が上がるケースも多いのです。
フランスの郊外で見た境界線が人生を変えた。高校時代の交換留学で移民の現実に触れ格差を自分ごとにした少女が、のちに中東へ渡って仕事づくりに挑むまで
この木製のしゃもじを日本の皆さんに届けるに至るまでのストーリーは少し過去に遡ります。
日本人女性オーナー大橋さんの最初の転機は、高校時代の交換留学でした。行き先はフランス。
移民が多い地域の郊外で、学校へ通い、夕方に街を歩き、週末は少し遠出をする。
日々の何気ない場面で、彼女は同じ都市の中に存在する境界線を何度も見たと語ります。
教育の機会、経済の選択肢、暮らす場所、漂う空気..
その差は目で見て分かり、肌でも感じ取れました。
そこで芽生えたのが、移民や難民の現実を「遠いニュース」ではなく「自分の近くにある課題」として捉える視点でした。
この実感が、のちの彼女の選択へと積み重なっていくのです。
大学時代に初めてヨルダンへ。2015年前後、難民家庭を訪ねて聞いた「帰れない」という信じられない現実。支援の熱が冷めると届かなくなる手、そこで芽生えた決意
大学生になった彼女は、中東への関心を持ち続け、夏休みを使ってヨルダンへ渡りました。
時期は2015年前後。
難民の家庭を訪問し、原郷での暮らしや避難の経緯、今の生活について話を聞きます。
家や家族を失い、隣国のヨルダンへ逃れ、いつ戻れるか分からないなかで暮らす不安に苛まれる人たち…。
最初は各国から集中的に支援が集まっても、年月とともに話題は薄れ、資金は細り、十分な教育や医療、生活費の確保が難しくなる現実を目の当たりにしました。
彼女はその話を受け止めながら、やがて「支援の波が引いても残るものとはは何か。」を考えるようになります。
短期的な寄付ではなく、日々の暮らしを支える雇用をつくること。
そこから逆算して、どうすれば仕事が生まれ、続いていくかという問いが、彼女の中に残りました。
2021年、移住という選択。首都はインフラが整い外国人も多い、想像より普通の暮らし。だから腹を据えて立ち上げに向き合えた、と語る胸の内
とうとう、彼女は移住を決めます。
ヨルダンに生活の拠点を置いたのは2021年の春から夏にかけての頃。
その年の11月には事業としての立ち上げに踏み出しました。
意外にもヨルダンの首都は、想像以上にインフラが整っていたと振り返ります。電気や水道といった生活基盤は安定し、カフェやスーパーなど、英語が通じる店も多く、海外のNGOや国際機関の関係者が集まる土地柄もあって、外国人の姿が日常に溶け込んでいます。
日本人居住者は決して多くはありませんが、生活は思っていたよりいい意味で“普通”だった、と。
安全面の実感があったからこそ、腹を据えて事業に向き合うことができました。
移住前の彼女は日本で難民の雇用を支援する会社に勤めていました。
扱っていたのはパソコン修理の分野。彼女にとっても、ものづくりや事業については何もかも初挑戦でしたが、働き口を生み、それを続けることをしたいという視点は、すでに心の内にありました。
素材の確保、乾燥、機械の精度、工程設計。ゼロからのものづくりで最初にぶつかった現場の現実
ヨルダンで商品のアイデアを考え、資源を探すうち、彼女が辿り着いたのはオリーブの木。
オリーブの栽培が古くから盛んな土地では、ありふれた資材として扱われるので、欧米や日本から見たイメージと違って、資材の使い道が限定され、意外と軽視されがちでした。
剪定枝や、実をつけなくなった木が切られると、その後は薪になるのが一般的。
活用されずに燃えていく木を、手仕事の材料として買い取り、仕事に変えられないか。そう考えるのは自然な流れでした。
しかし、立ち上げは簡単ではありません。
まず乾燥。木は乾かし方しだいで割れます。自然乾燥に長い時間をかける方法もあれば、設備である程度スピードを上げる方法もあります。
彼女たちは自作の乾燥設備を整え、含水率と割れのリスクの折り合いを試し続けます。
乾燥が済んだら、次は加工。精度が出る機械が見つからない・・厚みのズレが取れない、刃物の調整が合わない。ものづくりの第一歩は、道具と工程の確立に時間がかかる現実そのものでした。
最初の構想から外れ、根本的に企画の見直しも必要でした。
当初ボウルや皿のような立体的で難易度の高い品を想定しましたが、技術と素材の制約を見極めた結果、設計をシンプルに、工程を安定させる方向へ舵を切ります。
手を動かし、失敗し、また形を直す。その地道な繰り返しが続きました。
微細な形状のズレと格闘した日々。それでも木で作る意味を問い続けた作り手の覚悟。
「消費者の見えないところほど誠実でいたいんです」
彼女は、そう語ります。
ヨルダンではオリーブの栽培が古く、剪定材や実をつけなくなった樹がただの薪になることも珍しくありません。
彼女はその材を買い取り、道具として命をつなぎ直します。
木を切り出して指定の寸法で製材を頼み、工房に届いたら自作の乾燥設備でおよそ2週間かけて水分を整えるのです。
急ぎすぎれば割れてしまい、緩すぎれば歪む、温度と時間の綱引きです。
加工は三人の分業。
最初に粗形を抜き、次に柄と面を整え、最後に面取りと磨き。
はじめは「一気に大量に」の発想で機械の可能性を考えましたが、微細な厚みのズレが出て、仕上がりに納得がいかなかったのだそう。そこで工程を見直し、人の手で確認する密度を上げました。
木べらやスプーンで培った基礎を活かし、しゃもじでは米粒をつぶさない面の角度に特に気を配ります。
「木の面が鍋肌にそっと寄り添う角度があるんです。そこに気づいてから、艶が違うと感じました」
工房で働くのは、シリアやスーダン出身の人たち。
彼女は言います。
「みんな意外にも細かい精度まできちんと仕上げてくれます。
最初はやり方を知らなくても、一度学んだ手順を守り抜く真面目さがあるんです。日本のお客さまに出すものだからと、こちらの基準に合わせてくれることに、いつも救われています。」
ヨルダンという国の話も聞きました。
砂漠の国でありながら首都圏のインフラは整い、外国人も多く、英語の通じる店も少なくない。
ニュースで想像するよりずっと穏やかで安全で住みやすい国だと言います。
世界遺産ペトラに驚く友人を案内したこともあるそうです。
遠い問題を自分ごとに近づけるには、ものより先に物語を知ることです。
このしゃもじの背景には、そんな「人と人とのつながりの手触り」が確かにあります。
買い物は投票だとしたら。見えない誠実さに票を入れる。オーガニックな暮らしを当たり前にする一歩
IN YOU MARKETの理念は「全ての人にオーガニックな暮らしを。」。
このしゃもじは、農薬・添加物ゼロといった食品の尺度だけでは語れません。
環境にやさしい資源循環(オリーブ材の活用)、使っている炊飯器や土鍋を守る暮らしの知恵、そして何よりも難民の人々の雇用の場というかたちで、サステナブルとウェルネスを生活の手触りに落とし込みます。
「毎日つかう」ことが、遠くの誰かの「毎日いきる」を支える。
台所から始まる連携に、きっと価値があると信じています。
このしゃもじは、「買ってよかった」が続く道具だと感じます。
艶やかな一杯をすくうたび、ヨルダンの乾いた風、工房の木の香り、静かな集中、そして誰かのまじめな手つきが、想起され、ふっと台所に立ちのぼります。
台所からはじまるオーガニックな循環を、あなたの毎日にどうぞ。
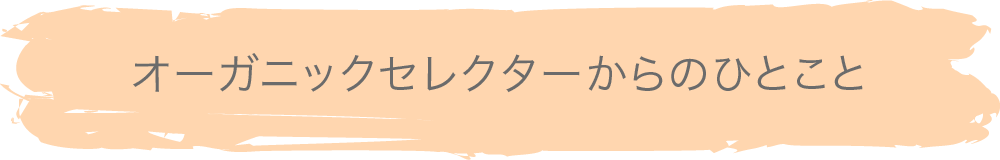
炊飯完了から60秒が勝負!木のしゃもじで艶と香りを最大化する「簡単3アクション」と、長く使うための手入れ
しゃもじを軽く濡らす。 木肌に薄い水膜を作り、米の付着を抑えます。
縦に切らず、面で起こす。 釜底からやさしく持ち上げ、空気を入れて立たせるイメージで。
鍋肌をなでる圧力は最小限に。 コーティングを守りつつ艶の層を壊さないことがポイントです。
手入れは中性洗剤+ぬるま湯でさっと洗い、すぐ拭いて風通しよく乾燥してください。お米の付着を長時間放置したままにすると取れにくくなってしまいます。
浸け置き・食洗機・漂白剤は避けましょう。
必要に応じて、オーガニックなオリーブオイルやココナッツオイルなどの植物油を薄くのばして乾拭きすれば、木肌のコンディションが整います。
遠い国の出来事は、私たちにはニュースの見出しでしか届きません。
けれども、このスプーンの背景には、静かに暮らしが続いている場所と、そこで真面目に働く人たちの時間が確かにあります。使うたびに、その穏やかさを思い出していただけたらうれしいです。
最初のレビューを書いてみませんか?